ずっと観てみたかった、『海がきこえる』を観た。
Filmarksのあらすじだけ読み、近所の映画館へ。子どものころは、毎年のように新作のジブリ作品を観ていたけれど、今振り返ると贅沢な時期だったなあと思う。
『海がきこえる』の舞台は、高知の高校。ところどころで映るかつおの絵や、主人公・杜埼拓の部屋から見える海の景色に、彼らの生活の海との近さを感じる。
作中、あまりに正直で、言いたい放題・やりたい放題の里伽子に、なぜだ、なぜなんだ……と何度も心のなかでつぶやいた。もし現実で里佳子のような人にあったら、たぶん私は速やかに逃げる。
けれど、彼女の言葉に、共感する自分もいた。
「自分を大事にして何が悪いの?社会が私を助けてくれるの?」という言葉に、彼女が置かれていた複雑な状況を想像する。彼女の環境と、彼女個人の資質からなる問題から、高校生の彼女は苦しんで、救いを求めていたはずだ。でも、高知の同級生たちがそれを彼女に与えることは、できなかっただろう。
求めているものを与えてもくれないのに、自分の一部を差し出せ、と言ってくるのは、彼女からすれば不公平なのだ。
今風に言うと作中の里佳子は「テイカー」なのだけど、彼女からすれば親やクラスメイトだって、彼女から何かを当たり前のように奪う存在に映るんだろう。
観ていて、おお、と思ったのが、拓の親友・松野豊の視野の広さだ。
社会をみるまなざしに、未来や過去といった時間や、他人をおけるようになると、自分の世界が、確かに現実とつながっていく。
長い目で物事を見ることができる、というのは成熟した人間にしかできない技を、中学3年生にして習得している松野。それに驚嘆して彼の親友になった、拓も、たぶんその素質のすばらしさに気が付く時点で、とても賢い人だったのだろうね。
あのころ嫌いだった人とも、久しぶりに会えばただ懐かしく、再会を喜ぶことができるようになる。
子どもの未熟さの、それでもきらめいて見えてしまう部分と、大人になることの良さを静かに両方描く、いい作品だった。


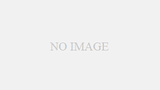

コメント