最近、FP2級の勉強を始めた。
数年前に3級を取り、そのころはすぐ実生活には役立つというわけではなかったけど、ライフスタイルが変わっていったここ数年、勉強したことが実生活で使う機会も多かった。
2級と3級は試験範囲が同じだから、覚えのある内容がほとんどだけど、意外と忘れていることも多いです。
勉強が終わったら、図書館で借りた「エッセンシャル思考」を読む。
20代前半ごろまで、いわゆるHow to本の読み方がよくわからなかった。
書かれている内容が、自分の身に入っていかないというか、読んだ1か月後にブクログやkindleに並ぶその本の表紙を見ても、内容がおぼろげにも思い出せない。
本を読むとき、私はいつも自分がその本の中に立っているような気持になる。別の世界に行って、読み終わると、現実に帰ってくる。その世界は現実とは関係していないけれど、ごくまれに、自分の生きている世界とつながることもある。
私にとって読書とはそんな行為の繰り返しで、たぶん現実と距離が近すぎる本は、あまりにも近すぎて、自分の中に言葉が入ってきづらく、よく読めないのだと思う。情報として、素通りしてしまう。
ただ、歳を重ねるうちに、そういった本であっても、自分が興味のある分野であると読める、ということを発見できた。自分の中にその分野の世界があれば、読める。普段の読書のように心や気持ちを持っていかれるのではなく、その心や気持ちを、どう動かしていくか、というシミレーションみたいな感覚で、読んでいる。またごくまれに、見た目はHow to本のようだけど、読んでみると、違う世界に来てしまうような本もあることも知った。
たぶん私は、自分が思っているより興味や関心の幅が狭いのだ。
若いうちはいろいろなことに興味を持って、なんとなく良さそうであったり、興味が出てきたものに端から取り組んでいくのが好ましいと、そう思っていたし、実際そうしてきた。でも、もう私はその時期を抜けているのだな、とこの本を読むと思う。
試すより、選ぶ時期。そして、何を選ぶか決めるのは、私であること。
自分の時間には限りがあり、大多数のことを、平等に扱うことはできない。
私はそのことを、つい忘れてしまう。すべてを大切にすることは何も大切にしていないのと同じ、という言葉は、何十回も聞いているのに。
でもそれは「トレードオフを無視したり非難したり」している状態で、いつか破綻するのだ。そのことの重みを、今は知っている。
そして、自分が選ばなかった結果として、大切なものごともろとも、自分以外に持っていかれるという残酷な事実も、身をもって知った。
選ぶ力を、必ず自分で持つこと。そして、選ぶための余裕、時間、遊び心、厳格な価値基準を持つこと。
未来に向けて多くの選択肢を吟味する時間と、捨てる時間と、今現在に集中する癖を作ること。選択肢は多いほうがいいけれど、行動は、多くなくていい。「これだけは」というものにだけ手をだすこと。
「より少なく、しかしより良い」を目指すこと。
少しずつ、実践していけるといい、と思えた内容でした。


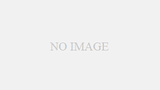
コメント