今月から会社を休職しております。
理由は様々ですが、4月からの人員不足のため業務量が増加→毎日22時過ぎまで残業→強い疲労感・頭の働かなさによるパフォーマンスの低下→受診→休職、という流れです。
診断は適応障害でした。
私の場合、とくにつらかったのが、①強い疲労感②頭がうまく働かない感覚でした。
とにかくなにをしても疲れ、土日ずっと寝ていても回復しない状態で会社に行くのがとてもつらかったです。
受診のきっかけと、診断を受けるまで
学生のころから、人と比べて疲れやすいことは自覚していました。ただ、フルタイムで働き始めてからは「常に疲れている」のが当たり前の状態だったため、実は疲労感だけの時はそこまで問題視していませんでした。(今思うと危険なサインであったのですが…)
自分の変化を自覚したきっかけは、頭の働かなさでした。休職する半月ほど前から、普段は1時間でできるような作業に3時間くらいかかり、ミスも連発。残業をしても翌日に仕事を持ち越すことが当たり前になり、かなり会社に行くのが辛かったです。
疲労感については「みんなこれくらい疲れてるだろう」と思って、あまり問題と思っていませんでしたが、以前の自分と比べて明らかに仕事のパフォーマンス(量・質ともに)が落ちて、このころから「なにか変かも?」と思うようになりました。
その後、なんとか残業時間を増やすなどで対応していましたが、
作業効率が落ちる→残業時間が増える→疲れる→作業効率が落ちる…のループへ突入。「これはなにかまずいことが思っている」と考え受診をした結果、適応障害の診断を受け、休職に至りました。
今の体調と今後について
休職してから2週間とちょっと休み、疲労感はだいぶ取れてきたと思います。まだ、買い出しで繁華街に外出をすると疲れる感じはありますが、1日休めば回復可能な程度です。頭の働かなさについては、仕事をしてないのでどれくらい回復しているかはわかりませんが、読書などは可能なレベルです。
診断書は1カ月で出していただきましたが、担当医から延長してもいいよ~と言われていることもあり、しばらくは延長しようかなと考えています。
理由としては、以下の3つです。
①今後働くにあたって、自分に合った働き方を見つけたいこと
②現職を続けるか、転職するか見極めたいこと
③部署異動が来年春まで難しいこと
①自分に合った働き方を見つけたい
甲状腺に持病があり、学生のころから疲労感が強かったです。同学年の子と比べると、なにをするのも疲れていて、やる気がない、遊びに行くくらいなら家にいたい…みたいな感じでした。
そのため、就活の時もあまり残業がない会社を選んだつもりだったのですが、実際は残業のある部署もジョブローテーションで回ることもありました。また、県外の職場に勤める夫と結婚したため、通勤時間もドアtoドアで1時間15分ほどかかるようになり、これも思ったより負担でした。(異動になれば短くなる可能性はありますが、本当に運次第で、正直あてになりません)
今の職場は「出勤してなんぼ」みたいなところがあるので、もう少し、疲労感の少ない働き方(在宅勤務や、休憩の取りやすいフレックス勤務など)ができるような職種に転向し、長く安定的に働けるようにすることが目標です。
コロナ禍でリモートワークを推進した企業がだんだんと出社回帰しているというニュースを見ると、元から在宅で働くようなスタイルの職種でキャリアを積む方向に変えるほうが長い目でみるといいのかなと考えています。
②現職を続けるか、転職するか見極めたい
現職でも在宅・フレックスを取り入れている部署もありますが、割合としては少ないです。
配属されるかは運の要素が強く、定期的に異動がある中、特定の部署に定年までい続けるのは現実的には難しそうです。
転職を考えていますが、具体的な企業・職種などはまだ決まっていません。転職エージェントなども登録はしていますが、エージェントとの面談はしていません。今は自分の中でこういう仕事をしたい!とか、興味のある!みたいなものを絞りこんでいきたい段階のため、実際に企業に応募する段階になったら面談などもしてみようかなと思っています。
③部署異動が来年春まで難しいこと
休職直前はかなり職場にいるのが辛く、その印象がいまだ強いため、現在の職場に戻るのは難しいと考えています。なので、もし復職するようなら異動が条件になるのですが、基本的に異動は毎年春に一度きり。復職する場合でも、年途中の復職は難しいかなと思っています。
最後に
今、精神的に会社に行くのが辛い、疲れがずっと抜けない、と思っている方がもしいたら、できるだけ早く長めの休養を本当におすすめしたいです。辛さや疲れは体温のように数で示せる基準があるわけではないので、自分で自分の状態を判断しにくく、「自分は大丈夫」「いつものこと」などと思ってしまいやすく、気が付いたときにはとっくに限界を超えていた…というときもあります。
この記事が、少しでも同じような状況にいる方の参考になればうれしいです。

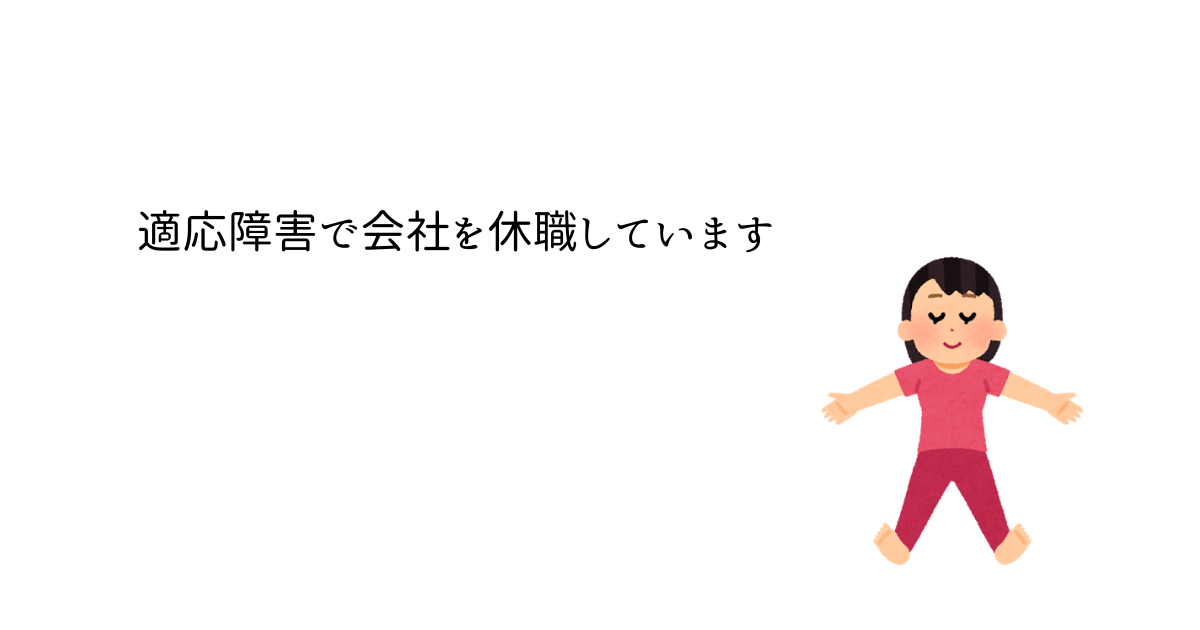


コメント